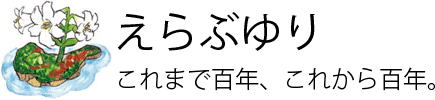えらぶゆり生産のあゆみ
【第12回】えらぶゆり栽培100周年
えらぶユリの栽培が始まったのはいつだったのか、100周年の記念日設定に当たって論議があった。
ゆりの取引については、明治35年、アイザック・バンティング氏の仕入れ主任、伊沢 九三吉 氏が来島して、市来崎 甚兵衛 氏にゆり集荷をさせたとの記録がある。
栽培はその前に始まっていたことになる。
明治31年、喜美留沖でイギリス船が難破し、助け出されたバンティング氏が野生のゆりを見つけ栽培を奨励したとの伝承があり、えらぶユリ栽培の始まりは、明治32年(1899)と定められた。
それから100年目に当たる平成10年(1998)をえらぶゆり栽培100周年記念年としている。
100年にわたって、本島の経済・文化に貢献してきた特産のえらぶゆりに感謝すると共に次の100年に向けた振興発展を願って、100周年記念事業が計画された。
記念事業として、公園や道路沿いなど、島内中にゆりの植栽を行い、ゆりの香りに包まれた4月にえらぶゆり振興大会等の記念式典や記念碑建立、記念誌の発行等が行われた。
その概要を記述する。
<記念式典の概要>
えらぶユリ振興の功労者の表彰
- えらぶユリ振興大会
基調講演「切り花生産からみたテッポウユリ球根生産の将来性」と題いて、大阪府立大学 今西英雄農学部長の講演 - パネルディスカッション
「えらぶユリ球根産地の将来性」について、指定商代表、市場代表、切り花産地代表、消費者代表、地元代表によるディスカッション - アイザック・バンティング氏の功績
えらぶユリの生みの親であるバンティング氏の末裔の招へいを計画し調査したが、氏の子孫はカナダのバンクーバで途絶えており、式典当日、知名町出身の留学生松元美幸さんがお墓に花を捧げて感謝の意を表した。
<えらぶユリ栽培100周年記念誌の発行>
- 元鹿児島県農業試験場花き部長・和泊町花き指導監 小林正芳氏編纂
第1部 100周年記念事業・えらぶユリ振興大会の基調講演等の内容を掲載
第2部 回想録 大学や農水省、県等の関係機関、指定商、各界関係者等からのえらぶユリとの係りを回想録として掲載
第3部 歴史編 生産販売の沿革、品種の変遷、栽培法の変遷、生産地形成の要因等、栽培100年の歴史を明治、大正、昭和、平成の年代毎にまとめてある。
第4部 資料編 ユリ根の生産販売状況、取引価格のほか沖永良部の気象状況等
付 ゆり百年歌詞 山口喜慶作詞、竿田富雄作曲
付 篤志寄附者御芳名 記念碑建立に当たり、生産者、関係各位、指定商社等からの寄付者名掲載
<永良部鉄砲ユリ百周年記念碑建立>
えらぶユリ発祥の地である喜美留の笠石公園の入り口に、生産者や関係各位の篤志寄附により「百周年記念碑公園」として整備された。
この1年間、えらぶゆりの歩みについて、自分自身が体験してきたことをもとに記述してきました。
えらぶユリは今年、栽培から118年を迎える。
花の嗜好は時代によって変わっていくが普遍的な美しさを持つユリは、いつの時代にも人々の心をとらえて離さないだろう。
今年、沖永良部空港の愛称が「えらぶゆりの島空港」と命名された。
今後ともえらぶユリが世界の人々に愛されることを願って、この項を終了します。
ありがとうございました。
【第11回】えらぶゆりの育種家
喜井 利一(きい としかず) 氏(1920年~1998年)和泊町喜美留
主な職歴:宮内省禁衛府皇宮衛士退役後、大島産業試験場、和泊町経済課長、永良部百合・フリージア生産出荷組合専務理事、えらぶ花き園芸組合専務理事等
喜井利一氏は、えらぶゆりの発祥の地で生まれ、若い頃からゆりの研究に熱心であった。
大島産業試験場や役場経済課で農業技師として農業指導にかかわるとともに、島の特産のえらぶゆりの研究に情熱を傾け、試験研究機関や種苗商社などとの幅広い人脈を活かし、新品種育成の地道な研究を続けていた。
戦後、アメリカから逆輸入されたジョージア種が輸出品種の主力になっていたが、ジョージアに勝る、大輪で耐病性、早咲きで栽培し易い品種育成を目指していた。
ゆりの品種改良は、交配、採取、植え付け、選抜を繰り返す根気のいる作業である。
氏は、役場の忙しい業務の傍ら、時には夜遅く黙々と交配や植え付け作業を行う姿があった。
その成果が実を結び、昭和50年「えらぶの光」、昭和59年「きびる」、昭和63年「えらぶの彗星」を作出し、農林種苗品種登録されている。
その後も「リイゲン」「リイチ」等を作出している。
氏の功績は広く受け継がれ、ゆりを始め、キクやグラジオラスなど花の島として地域に定着している。
小林 正芳 (こばやし まさよし)氏(1931年~2014年)

小林 正芳氏
主な職歴;鹿児島大学農学部卒、農林省九州農業試験場園芸部花き研究室勤務後、鹿児島県農業試験場に移籍、花き研究員として勤務、鹿児島県農業試験場花き部長、定年退職後、和泊町花き指導監等
戦前戦後は、在来品種の「アンゴー」種が輸出用主力品種であったが、国内向け需要の高まりから、ゆり組合と連携し、「ひのもと」種の導入や輸出用「ジョージア」種の栽培技術改善に尽力した他、機械化・省力化の推進等、えらぶゆり産地確立に貢献した。
また、ゆり需要が増大する中で、病害虫の発生、ウィルスによる品質低下、輸送中の球根腐敗、ネダニの発生等、次々と起きる諸問題に対処するため、他の研究機関との情報提携や現地試験を実施した。
特に、ネダニ被害に対するダイジストンの施用、親子リンペン繁殖法の推進、球根消毒による腐敗球防止、摘花剤による球根肥大と省力化、機械化の作式改善等を推進された。
昭和46年、国の指定試験としてテッポウゆりの育種に取り組み、昭和53年、「おきのこまち」「おきのかおり」昭和56年、「おきのしらたえ」が農林登録された。
氏は、本町の町制施行50周年記念事業に「世界のゆり170種」10万株を一斉開花させ、「国際ゆりシンポジウム」や「NHK素人のど自慢大会」を開催して、花の町のPRに貢献された。また、平成10年、えらぶゆり栽培100周年に当たっては、「えらぶゆり100年誌」の編纂責任者として、貴重な資料を纏められた。
次回は、えらぶゆり栽培100周年事業の取り組みを紹介します。
【第10回】(株)沖永良部球根バイオ研究所の設立
メリクロン球の導入でゆりの品質向上が図れることが実証され、県フラワーセンター等からの優良球根の供給体制ができたが、より安価に、より早く供給できる体制として、地元にバイオ施設整備の要望があった。
【第9回】組織改革と品質改善への取り組み
沖永良部台風後、品質低下で国内外から信用を失墜したえらぶゆりは、バイオ技術によって品質改善が図られ、高い評価を得ることができました。
しかし、ゆりを取り巻く環境は一層厳しさを増していき、1985年9月のプラザ合意後、急激な円高が進み、輸出環境が一段と厳しくなり、商社側から需給バランスに基づく計画生産の徹底と販売体制の統一が求められました。
【第8回】バイオ技術を活用したゆりづくり
ゆりづくりで最も注意すべきは、ウィルス病対策である。
一度ウィルスに感染した罹病球根は、回復することも治癒することもなく、抜き取って焼却処分か埋設処分しなければならない。
畑の隅に放置するとアブラムシによって、次々と伝染しウィルスが蔓延する。
えらぶゆりが経済作物として増産されると、ウィルス病も多発するようになった。
特に、沖永良部台風後は、管理作業も疎かになったこともあり、病気が蔓延し、切り花産地からクレームが続出、産地崩壊の危機に至っていた。
品質改善協議会において、「えらぶゆりがウィルス病や腐敗病に侵され品質低下が数年続き、国内外においてえらぶゆり離れが深刻となっている。」、「米国は数年前から輸入を中止し自国生産に切り替えた。オランダでもえらぶゆりの品質低下で損害が生じ、4~5年前から球根生産を始めた。」といった問題が取り上げられている。
このような現状を打開するため、当時研究段階にあった、バイオ技術によって品質改善に取り組むことにした。
ゆりの増殖は一般的には栄養繁殖のため麟片で行うが、麟片ではウィルスも継承される。
茎頂培養法は、ウィルスに汚染されていない生長点を0.3mm~0.5mmで摘出し培養する方法で、ウィルスに汚染されていない無病球根を生産することができる先端科学として期待されていた。
バイオ技術の実用化については、大学や研究機関、更には企業でも事業化の取り組みが行われていた。
当時、本島と関係のあった企業に、島の窮状を相談し、ゆりの茎頂培養による無病球根の供給を依頼した。
相談先の企業では、大量増殖体制を整備し、地元の要望する、年間10万球を昭和58年から5年間供給する。
品種は、輸出用のジョージア種とした。
価格は、1球100円で年間1,000万円の多額の投資であるが、えらぶゆりの品質改善と信頼回復に関係者一丸となって取り組んだ。
多額な負担は、行政と生産者、集荷責任者、指定商社で分担することになった。
それ程、えらぶゆりは厳しい状況に追い込まれていた。
昭和58年、最初のメリクロン球ジョージア種10万球が到着する。
フラスコで育てられた極小球であった。
このメリクロン球を大事に育て、種球更新を図り、3年目で生育の揃った無病のゆり生産ができるようになった。
メリクロン球の普及で品質改善が図られ、信頼回復の期待が高まっていたが、為替相場は更に円高に進み、輸出用の需要が低迷し、せっかく品質回復したゆりを生産調整する事態になっていた。
為替相場の変動は、ゆり販売に大きな影響を及ぼし、なお一層の計画生産の徹底やコスト削減が求められた。
次回は、組織改革の経緯を記述する。
【第7回】沖永良部台風後のゆり事情
南西諸島は台風常襲地帯で、台風時期を避けた作物が定着している。
さとうきびは毎年のように被害を受けるものの、収穫ゼロにはならないことから、地域の基幹作物として位置付けられている。
沖永良部では、ゆりは9月に植え付け、6月に収穫できる。 生育期の冬場は、季節風による塩害を受けるが、潮風には強い作物であることから長年本島の特産品目として定着している。
昭和40年から昭和50年にかけ、飛躍的に増大したえらぶゆりは、品質改善を図りながら市場ニーズに対応できる産地体制の強化が図られていた。
そのような国内外の需要の高まりに、安定供給体制が取られ、大型トラクターの導入等機械化体制も整っていた矢先の昭和52年9月9日、台風9号(沖永良部台風※気象庁サイトへ)の直撃を受けた。
農家では、ゆりのほ場の耕運や種球の選別を終え、台風通過後、植え付けを行おうと準備し、種球も倉庫の入り口に積み上げてあった。
台風9号は、907mbと地上観測で最低の気圧を記録する最強の台風で、全島に甚大な被害をもたらした。
台風は、翌日には九州北部に達し、天気回復したが、人家、倉庫等全ての建造物が被害を受けた。
倉庫が倒れ、ゆり種球は散乱し、ほ場の片付けなどに追われた。
島全体で復旧工事が始まり、労力が不足する中で、農家は、ゆりの植え付け作業を優先させていた。
植え付けの終わったほ場では、品種の混りやウィルス罹病株の多発生、アブラムシの多発生等が見られ、翌年の植物防疫所の栽培地検査において不合格圃場が増大した。
その大きな要因は、ゆりの栽培管理に手が回らなかったことが挙げられる。
その年収穫され出荷されたゆりは、切り花産地において、ウィルス病を多発させる等、切り花農家に多大な損失を生じさせると共にえらぶゆりの信用を失墜させることになった。
特に、輸出先のオランダからは、「日本産テッポウユリのウィルス汚染球の割合が急速に増加し生産者の不満が高まっている。」との調査報告があり、早急な品質改善対策が求められた。
えらぶゆり組合では、関係機関と連携し、防除体制や親子リンペンの徹底等による、品質改善の取り組みを推進した。植物防疫所では、栽培地検査を、予備検査、本検査と2回検査体制にして、ウィルス病撲滅に取り組んだ。
そのような、支援体制のもと品質改善の回復が図られていくが、一度失った信用を回復することは容易でなく、オランダでは、自国のゆり育成を本格化させたといわれている。
更に、当時、新技術として研究されていた、バイオ技術による新品種育成及び大量生産技術が事業化され、次々と新品種が育成され、えらぶゆりの需要がオランダ産にとって代わるようになってきた。
その背景には品質が大きく関わっており、本島でもバイオ技術を活かした品質改善が早急な課題であった。
次回は、バイオ技術によるゆりづくりについて記述する。
【第6回】フリージアの生産状況
今回は,えらぶゆりと同様に,島の特産品として愛された「フリージア」生産の歴史を紹介します。
沖永良部島では日本復帰後、従来の自給的農業生産から収益性の高い換金作物生産への模索が始まっていました。
さとうきびは黒糖生産から大型分蜜糖工業化が進み、また,ゆりは国内外の需要が高まり,増産体制に移行していましたが、ゆりに次ぐ品目として導入されたのが、南アフリカ原産のフリージアでありました。
和泊町では、日本復帰後の農業振興策として,国や県の指導のもと、需要の見込めるフリージアの試験栽培に取り組んでいきます。
フリージアの品種も種苗商社や試験場等の協力で,多くの品種が試験栽培されていましたが、その中で”ラインベルト・ゴールデンエロ―”が有望品種として奨励されていました。
島民はゆりとフリージアの二大球根生産に熱心で、その後も色々な品種の試作を続け、フリージア産地としての地位を築いていきました。
当時,国内のフリージアは、生け花用としての需要が高く、経済成長に伴い人々の生活も豊かになり,花の需要も急激に伸びていた時期でした。
そのような需要に対応するため,フリージアの生産は、需要に見合った計画生産、計画出荷が重要であり、その為には強固な組織体制が必要でありました。
それを受け,昭和39年、これまでのフリージア組合を「沖永良部花卉球根生産販売組合」に改名し、生産指導や計画生産等の指導に取り組んでいくことになります。
しかし,当時,販売を担当する商社組合長から「フリージアの戦前の産地は父島・母島であったが、戦後は,八丈島で栽培されている。世界の花卉球根産地の中でフリージア産地の栄枯盛衰変動は大きい。」と挨拶されています。
この商社組合長は,フリージアはアヤメ科の植物で、連作の出来ない作物であることから、産地が移動することを予見していたと思います。
島内のフリージア生産が増えるに従い、畑一面に咲き誇る黄色い絨毯を敷き詰めた花の島と紹介され、えらぶゆりと並ぶフリージアの島のイメージが大きく、観光資源としても活かされるようになりました。
早春には,フリージアの香りに包まれた南の島のジョギング大会に,全国から多くのジョギング愛好家が集い賑わいを見せていました。
本島で生産される主力品種のラインベルト・ゴールデンエロ―は、大輪の濃い黄色で,甘酸っぱい香りが特徴で、全国の切り花産地で栽培され11月から6月まで出荷されていました。
フリージアの使われ方も昭和の時代、床の間の生け花や稽古花として使われていましたが、近年、オランダ産の花茎の長いフリージアが好まれるようになり、花束やフラワーアレンジメント用としての需要が高まり、ライフスタイルの変化などからフリージアの用途も変ってきました。
オランダで改良された花茎の長い品種が好まれてくると、球根生産もオランダの気候に近い産地に移っていき、現在は種子島で盛んに栽培されるようになっています。
次回は、ゆりに話を戻し、昭和52年に襲来した、未曾有の沖永良部台風後のゆりの状況にて記述します。
【第5回】変動為替相場制後のゆり事情
第2次世界大戦後世界の平和が保たれ、我が国の経済も固定相場制のもとで輸出産業が急速に発達してきました。
経済成長に伴いゆりの需要も増大し、国内、輸出共に史上最大に達しましたが、我が国の急激な輸出増大は世界の貿易不均衡を招き、昭和46年のニクソンショックやスミソニアン合意で大幅な円の切り上げが行われ、更に2年後には変動為替相場制へと移行していきました。
以降、円高が進み輸出産業は大きな打撃をこうむりますが、製造業を中心とした工業は技術革新や効率化により対応を図り、より強固な産業構造を築いていきました。
ゆりづくりも機械化や栽培技術の改善で生産性の向上は図れたものの、為替相場に対応するコスト削減には限界があり、輸出先のオランダ国からの需要が減退してきました。
また、オランダやアメリカでは割高になった日本産の代替として自国産の育成に力を入れ、ブリーダーと呼ばれる育種家が活躍し、自国産のテッポウゆりを生産し供給する体制に変わっていきました。
本島の輸出用品種である「ジョージア」は、早咲きで多輪である等、品質面での評価は高く根強い需要に支えられ生産を続けてきましたが、日々変わる為替レートにゆり価格の対応ができない状況にありました。
1ドル360円からどんどん円高が進み、300円、250円、150円、100円と、自分たちの身の回りに関係のない世界でありましたが、ゆりの価格は円高・ドル安、更にはオランダの通貨であるギルダーとの為替レートも関係し、大都会から遠く離れた離島の経済に為替相場が大きな影響を及ぼしていました。
えらぶゆりは、為替相場や需要と供給の市場原理に連動する商品であり、島民はゆりを通し、経済情勢に敏感な社会性を身につけてきたと考えます。
ゆりの輸出が厳しくなる中で、国内の花の需要は増大しており、新たな品目としてフリージアの需要が高まってきました。
次回は、フリージアの生産状況について記述したいと思います。
【第4回】ゆりの販売体制について
ゆりの販売は、もともと生産者個々が商人を通じ販売していましたが、生産が増えるに従い生産や販売体制の組織化が図られるようになりました。
基本的には商社との専属グループ制でありましたが、全体的には、生産組合と商社組合の、両組織が協力しながら発展してきたと考えます。
ゆり取引の大きな特徴として、①えらぶゆりの商品は球根(種)である。②沖永良部島が遠隔離島である事が挙げられます。
球根生産は天候に左右されやすいことや球根の大きさによって用途、需要が異なります。また,離島ゆえ交通面のハンディーがありました。このような条件の中で、安心して生産し代金回収の出来る仕組みを先人たちは築いてきました。
太平洋戦争後復活したゆり取引は、米軍政下で本土への渡航が自由にできなかった時期、価格を電報で連絡し合い、1ドル360円の公式レートでエルシー取引が行われました。
この取引は、最近まで供託金制度としてゆり取引の基本でありました。
また、昭和26年から輸出貿易管理令による輸出品目として承認され、輸出振興が図られました。
更に、日本復帰後の昭和29年から価格協議会も輸出百合根中央会の主催で東京の参議院議員会館で行われております。
協議会には農林省、通産省、鹿児島県が立ち合う中で行われていました。
昭和37年から、生産販売改善協議会として鹿児島県の立ち合いの下、産地側と商社側で協議を行い、ゆりの生産販売の安定化が図られてきました。ゆりの販売体制はこの時期に確立されたと考えられます。
即ち、産地組合が取引商社を指定し、指定商社と荷造を行う集荷責任者と生産者が専属グループとして連帯感を強めた組織となってゆり生産・販売体制が整っていきました。
【第2回】昭和40年代のえらぶゆり球根の生産状況
昭和40年代のえらぶゆり球根の生産状況
第2次世界大戦前まで欧米の国々に輸出されていたえらぶゆりは、戦争によって輸出が途絶え、栽培も禁じられていましたが、先人たちは秘かに種球を守り、戦後すぐにゆり球根の生産を始めております。
戦後、奄美の島々は日本と分離され米軍統治下におかれ本土への渡航ができなくなりました。その中でゆり生産を復活させ、昭和24年、米軍政下で輸出が再開されております。
奄美群島が日本復帰した昭和28年以降、欧米でゆりの需要が高まり、ゆり増産に拍車がかかり、生産量が増大していきました。
昭和40年代は、我が国が戦後復興を成し遂げ、急激な経済成長に伴い、社会全体が大きく変化してきました。
経済成長により地方から都会への人口流出が進み、食料品の需要増大と併せ花の消費も増大していきました。
えらぶゆりも戦前までは、欧米諸国への輸出商品として栽培されていましたが、国内の切り花産地からも温室栽培用切花球根の需要が増大し、大量生産体制に移行していきました。
また,本島の農業も大きく変わっていきます。
我が国のコメの過剰により、水田転換が進められ、需要の増大していたさとうきびの増産が図られ、同時に、大都市向けの輸送野菜や肉用牛子牛の需要増大等、従来の自給的生産から換金性作物生産へと農業構造が大きく変わっていきました。
更に、奄美大島特産の大島紬の需要が高まり、大島紬の機織りも盛んになっておりました。
限られた労力で生産拡大に対応するため、土地基盤整備が進められ大型トラクターが導入され農業の機械化が推進されていきました。
ゆりの生産も規模拡大が図られ生産量も飛躍的に伸びていきました。
ゆりの品種もこれまで野生種からの選抜や種苗商社からの導入種が中心で、「アンゴー」「佐伯30号」「植村青軸」「殿下」「城山」等、多数の品種が栽培されていましたが、昭和29年アメリカから導入された「ジョージア」と昭和40年福岡県の中原喜右衛門氏が育成した「ひのもと」が導入され、輸出用、国内用として栽培され、えらぶゆりの二大品種として生産拡大が図られていきました。
次回は、急激に増産されたゆりに発生したトラブルやその改善策等について、記述します。